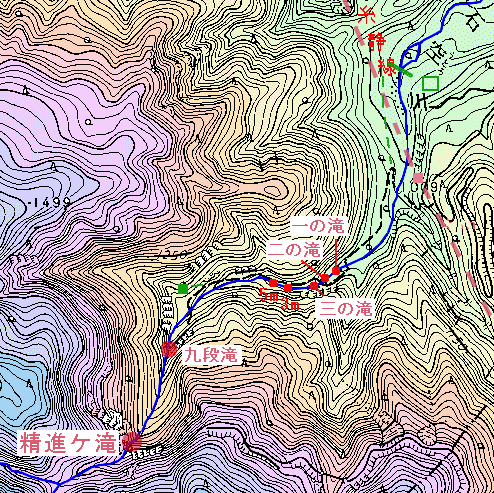 石空川の滝位置図
石空川の滝位置図●国土地理院2.5万地形図から作成しました。地図には、現在の遊歩道の記入が一部無い。
●現在の遊歩道は、図の緑四角の附近に無料駐車場があり、トイレもあります。
●緑線の所に、鉄製の吊橋があり、左岸に渡り、左岸ぞいに緑点線の道(位置は適当です)があって、以前の図の点線路に合流する。この遊歩道は滝見台まである。山道としてはしっかりしているが、足ごしらえは必要な道です。
滝見台は、図の緑印。
滝見台下から先の点線路は不明瞭
私達は、九段滝の下まで行きました。精進滝の滝見台から踏み跡がありましたが、ルートを外れるとちょっとあぶない大石渡りをする。
●武川村側から遊歩道入口に至る区間の精進滝林道は去年秋から通行止になっていたが02/09/14日から開通する予定だそうです。私は、御座石鉱泉側から廻りました。
●図の1009附近から川に下がる道は行きませんでしたが、川を渡る部分は川沿いからは、道形が見えませんでした。地図の通りの地点だと、洪水で削られた崖上で行き止まるかも。
●図の下の、精進滝に東のほうから向かってくる林道は、精進滝林道から枝分かれする林道で、途中の橋が遊歩道入口付近から見えますが、何年も前から通行不能で、歩きでも無理みたい。→この記録参照。HP「白州みちくさ案内」 んがお工房さんのHP
●地元にて聞き取り。滝見台の下から、九段滝の右岸を大高巻して精進滝下に出るルートがある。しかし、地元の人も入る人が少なくなり、荒れていて、安全は保証しないor危険。時間もかかるそうです
なお、精進滝の下までいった方のHP記録はこれ→丹沢の滝のページ。
それによると、九段滝と精進滝の間に、下から見えないけど、立派な滝があるとのことですね。
沢登り、岩登りでは、精進滝上の北沢・南沢とも、溯行対象になっていますから、文章の記録があると思います。 国土地理院2.5万地形図鳳凰山より作成 段彩は50mごと
 吊橋(精進ヶ滝橋)上流にある巨大堰堤。完工間もないらしくまだ埋まっていない。
吊橋(精進ヶ滝橋)上流にある巨大堰堤。完工間もないらしくまだ埋まっていない。川はものすごい土石流河川。
 吊橋上より望む河原。画面下端の巨岩は、長径5m以上ありそう。
吊橋上より望む河原。画面下端の巨岩は、長径5m以上ありそう。両岸の地質は、ここでは桃の木層群の黒色の泥岩だが、河床は白色の甲斐駒花崗岩の巨礫が優勢。
洪水時に、これらの巨礫が土石流となって移動しているらしい。
後で見る上流の滝の部分に比べて川の水量がなく、河床礫の中に浸透しているらしい。下流の堰堤の影響もありそう。
 糸魚川静岡線沿いの支流の合流点附近の本流河原。
糸魚川静岡線沿いの支流の合流点附近の本流河原。花崗岩の巨礫が堆積し、河原の中央が高くなっているという土石流堆積の形をしている。
右手の崖は、段丘になっていて遊歩道がある。
過去の土石流堆積面だが、年代はごく新しいものらしい。
地図の糸静線より南の地質は、甲斐駒ヶ岳深成岩体の甲斐駒花崗閃緑岩になる。
 一の滝(魚止め滝)。上の滝は、二の滝。
一の滝(魚止め滝)。上の滝は、二の滝。この上流、5m滝まで大小5つの滝があり、連瀑帯(瀑布帯のうち滝が近接して連続しているもの)になっている。
<滝の形> 滝高:5m。
面滝・円弧型・急傾斜・全面滝壷・細節理花崗岩型
滝壷は埋まってます。
連瀑、瀑布帯の解説 →こちら。
面滝・円弧型・急傾斜・全面滝壷の解説 →こちら
←画面にカーソルを載せると、滝面・滝崖等を表示
細節理花崗岩型:花崗岩は侵食作用の面からみると節理面(冷却して収縮し固化する際にできる割れ目)にそって割れる性質があるので、節理面が密に入っているのと粗く入っているので、侵食される形が違ってくる。これは節理が密に入っている花崗岩タイプの岩という意味・・岩質は花崗閃緑岩だけど別にいいや。
 二の滝(初見の滝)。
二の滝(初見の滝)。連瀑帯の中で、一番大きな滝。
<滝の形>
滝高:16.5m。写真の水の落ちている所は13.5m
面滝・両溝型・直下・全面滝壷・細節理花崗岩型
増水時には、左の落ち口からも落ちる。滝上で見ると、中島になっている。このタイプの滝面を両溝型と呼ぶことにしました。
両溝型:割複合型滝面のうち副滝が川の両岸近くにあり、滝の中央に中島がある,二条になって落ちる形のもの。張出し型(中央部分が平面で張出し、平常時に二条になって落下するが、滝上の地形は平らで、目立った溝が無いタイプ)から侵食が進んだ複合型滝面。
岩質が硬質だが、割れ目があって大きくブロックで割れやすい花崗岩類の滝によく発達する傾向がある。
←画面にカーソルを載せると、両溝型の説明図を表示
 三の滝(見返りの滝)。
三の滝(見返りの滝)。二の滝のすぐ上流にあり、以前の二の滝の上部が分裂して上流に移動した滝である。
二の滝の川幅(水の落ちている幅ではなく、平坦な谷の幅)に比べて、川幅が半分に狭くなっている。
残りの川幅の半分は、写真の階段のあがる所ですが、川の水面より少し高い段丘状の地形になっています。
この地形を、上滝岩石段床となずけることにします。
この地形については、項を改めて→作成中
<滝の形>
滝高:4.5m。
線滝・壁状・直下・全面滝壷・細節理花崗岩型
線滝の解説:面滝とペアの用語です。こちらをみよ→ここ
一見、川幅が変わらないから面滝にみえるんですが、この滝から上流の3m滝、5m滝までの部分がその上流・下流に比べて、ぐっと狭くなっているので線滝にします。
左上の浮遊霊のようなのは、レンズの汚れ。(^_^;)
 三の滝の脇の段丘状の岩段上にある谷斜面から転げ落ちてきた花崗閃緑岩のブロック崩壊の巨岩。
三の滝の脇の段丘状の岩段上にある谷斜面から転げ落ちてきた花崗閃緑岩のブロック崩壊の巨岩。本流の土石流礫のうえに乗っている。
写真のように、節理に沿って風化により割れている。
河床の土石流で運ばれている巨礫は、このような大きな花崗岩ブロックが節理面に沿って割れてできたもの。
 九段の滝
九段の滝滝見台から。滝の上部しか写っていない。
上に精進ヶ滝があるので、付録の滝みたいにみえるが、滝高さ46mともいわれるスゴイ滝である。
<滝の形>
●滝高:46m(武川村史による)・・・実は、15間をm換算すると
45.5m→四捨五入で46m ということがあるんで、一抹の不安がある。昔、15間と書いてある資料があって、それを換算して写しているだけじゃないんだろうか。測ってないんだが、計測した方がいいかも。
●上部:線滝・階瀑・直線溝型・急傾斜、
下部:面滝・複合型、副滝円弧状直下・部分滝壷?(埋没)・主滝壁状・階瀑・中傾斜
細節理花崗岩型
このような、デカイ滝になると、滝面の上と下で(あるいは中部で)形が変わってきます。滝上から落ちて、下まで行くあいだに一気に落ちない場合は、岩にあたって水の落ち方流れ方が変るから当然なんですが。
高い滝の滝面地形をどう考えるかは、項を改めて→作成中。、
せっかく、滝の下まで行ったのですが、なんとカメラは失敗して写真とれず。下から見ると、壮大で凄い滝です。
上部の狭い線滝から、下部が、広がった複合滝面になっているのもよくわかったのだが・・・残念(T_T)
 精進ヶ滝
精進ヶ滝滝見台より。滝の上の2段分しか写っていない。
木をすかして見ると、4段の階瀑に見えます。
段瀑と階瀑についての解説は、長いけどこれを見てね。
<滝の形>
●滝高:121m(武川村史による)への懐疑・・・これどうやって測ったんでしょうね。正確そうで、かなり怪しそうな値です。実は、40間をm換算するとぴったり121mになるので、40間の換算値じゃないかと凄く疑っています。
そんなら、測って確かめたらいいじゃないかということになりますが、こんな巨瀑になると、測るのは簡易測量では困難です。また、武川村史の記述はなかなか正確なんだよな。というわけで
なんともいえませんね。
●精進滝は、岩質は花崗岩と地質図になっていますが、精進滝とそのならびの岩壁(地図上で一直線で、普通の滝崖でなく硬岩の存在を示唆します。
滝見台からは、この岩壁が、千葉県の鋸山の石切り場の壁みたいに見えます。
遠望ですが、精進滝の滝面は、節理のほとんど入っていない緻密な岩質のようで、九段滝や滝見台より下流の1〜3の滝のような節理の細かく入った花崗岩とは岩質が異なり、のっぺりした垂直のスラブになっています。記載のない火成岩の岩脈が入っているんでないかなあ。
地質の説明で、アプライト(深成岩体に後で貫入して岩脈になる、緻密な細粒の火成岩)の岩脈が甲斐駒花崗岩には見られるという記述があるので、それなのかなあ。
●滝の地形は、上部・線滝・階瀑・直下・・、粗節理花崗岩か□□岩岩脈?型。細かいことは遠くて分かりません。